こんにちは!まめちゃんです。
突然ですが、みなさんは文章力に自信がありますか?
私は、正直、苦手で自信はありません。
頭ではこう伝えたいとは思ってはいるものの
いざ、文章にするとうまく相手に伝えられない
これではブログの記事に影響がでてしまう…
みなさんも
「文章が下手だから読まれない」
「何を書けばいいかわからない」
と悩んでいませんか?
そんな人にこそ読んでほしいのが、Webメディア「ナタリー」の元編集長・唐木元さんによる『新しい文章力の教室』です。
この本は、「伝わる」「読まれる」「完読される」文章を書くための実践的なテクニックが詰まった一冊です。
本記事では、本書の要点を5つに絞ってわかりやすくまとめました。
結論 『新しい文章力の教室』から学べること

本書で学べる5つのことは
- 書く前に考える(=設計)
- 「何を伝えたいか(主眼)」を明確にする
- 情報を読みやすい順に並べる(構成力)
- 無駄・曖昧な言葉を削る(推敲力)
- 一気に書いて、あとで直す(作業分離)
この考え方を身につければ、読みやすく伝わる文章が誰にでも書けるようになる。
それが本書の一番大きなメッセージです。
書く前が9割|まず「何を書くか」より「何を伝えたいか」

本書で最も強調されているのが、「書く前の準備」の重要性です。
文章を書くことは、頭の中の情報を整理して設計する作業
- 何を伝えたいのか?
- 誰に向けて書くのか?
- 読者にどう感じてほしいのか?
これらを明確にすることで、文章の流れがスムーズになり、読みやすさが大きく変わります。
完読される文章とは「情報を配置する技術」で決まる

「読みやすい文章」とは、言い換えれば「構成が明快な文章」です。
唐木氏が紹介する基本構成は以下のような順序
- 主眼(何を伝えたいか)
- 補足情報(背景・文脈)
- 具体例
- まとめ・言い換え
この「ナタリー式の型」に当てはめるだけで、情報が自然と頭に入る構成になります。
曖昧表現・冗長表現を避ける

読み手にとってストレスになるのが、曖昧で回りくどい表現
本書では、次のような言葉は削るか具体化するように勧められています。
- 「〜的な」「〜において」「〜と思います」
- 主語が曖昧な表現
- 過剰な形容詞や副詞
文章は「端的で具体的」にすることで、ぐっと読みやすくなります。
書きながら直すのはNG!まずは書き切る!
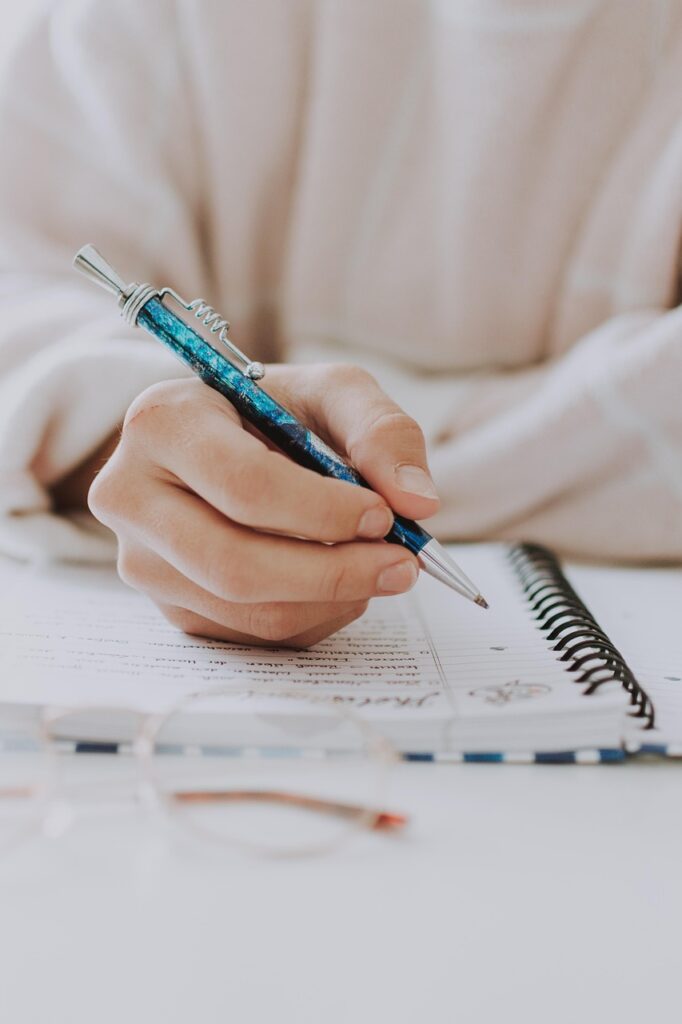
文章が苦手な人ほど、途中で立ち止まってしまう傾向があります。
唐木氏は、「まず最後まで一気に書き切る」→「後から推敲する」という二段構えを推奨しています。
この「分業型の書き方」によって、書くスピードも精度もアップします。
推敲で「伝わる文章」に仕上げる
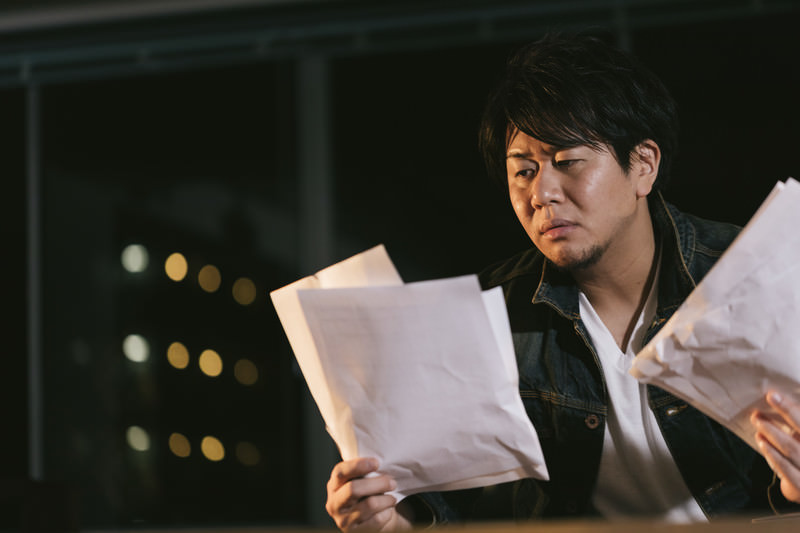
書き上げた文章を読み返すときは、「主眼がズレていないか?」「不要な言葉はないか?」を確認します。
特にチェックすべきポイント
- 最初と最後に一貫性があるか?
- 読者が知りたいことに答えているか?
- 「一文一意」になっているか?
このチェックリストを活用することで、文章の完成度がぐっと高まります。
まとめ
『新しい文章力の教室』は、以下のような人におすすめです。
- ブログ・SNS・レビューなどを書く機会がある人
- 書くのが苦手、時間がかかると感じている人
- Webライター・編集者を目指している人
- 「文章力を根本から鍛えたい」と考えている人
文章力とは、センスではなく技術。
この本は、その技術を実践的かつ丁寧に教えてくれる「文章のトレーニング本」です。
最後までお読みいただきありがとうございます。
「文章を書くのが苦手」「伝わらない」と感じていたら、ぜひ一度この本を手に取ってみてください。
新しい文章力の教室
Amazon
https://amzn.to/4qnUNCI




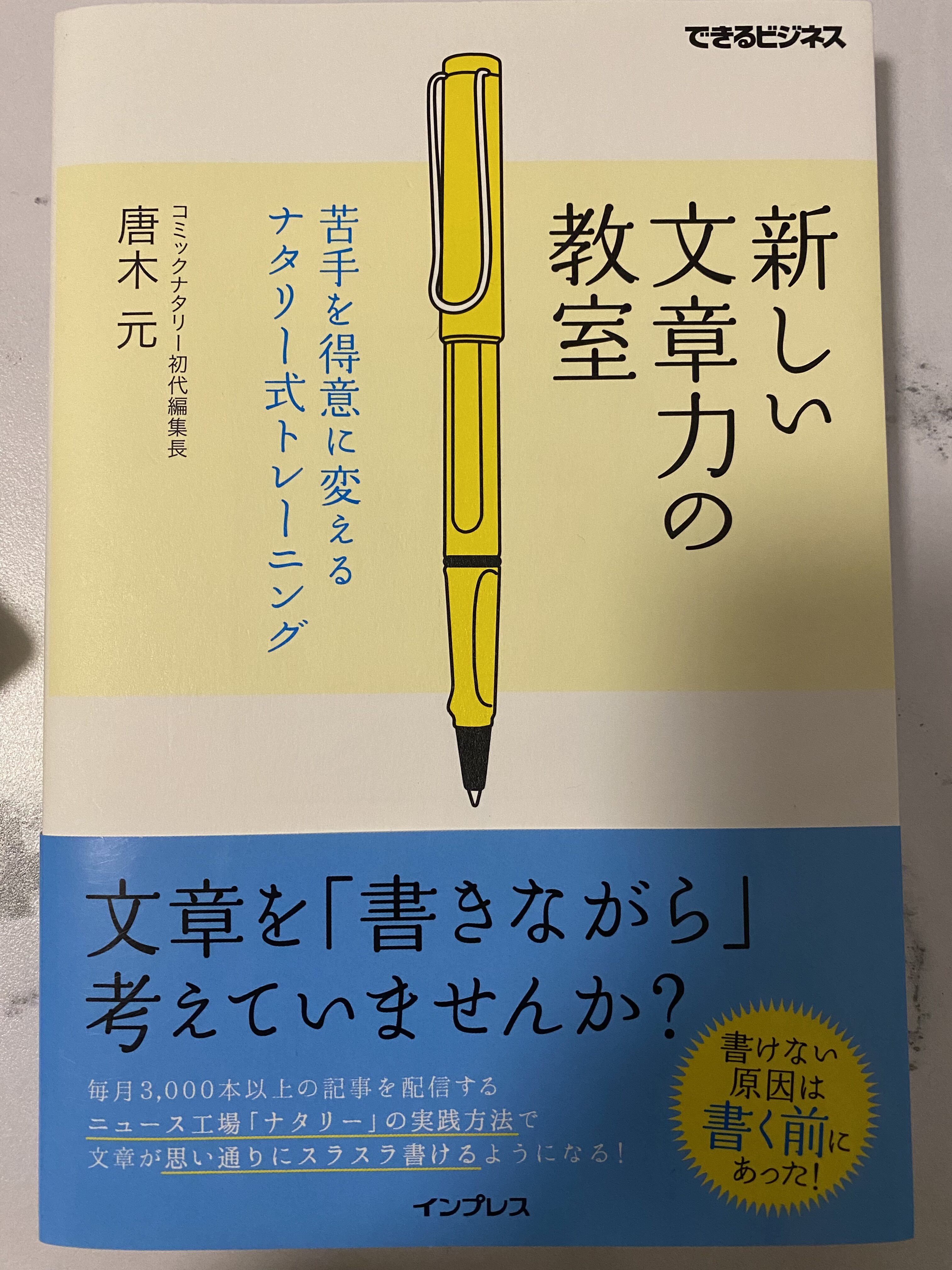


コメント